七月 夏土用 【なつどよう】

- 滋養強壮
- 疲労回復
- 暑気払い
暑さが厳しい時期、体を休めて精をつける
「土用」とは、季節の変わり目となる立春、立夏、立秋、立冬それぞれの前日までの約18日間のことで、「春土用」「夏土用」「秋土用」「冬土用」があります。なかでも立秋前にあたる「夏土用」は、一年の中で最も暑さが厳しく、特に体調管理が必要な時期であったため、土用と言えば夏土用を指すようになりました。
土用の起源は諸説ありますが、有力とされているのが中国から伝わった「陰陽五行説」に基づくものです。この説では、自然界は「木・火・土・金・水」の五つの要素から成り立つとされ、春は「木」、夏は「火」、秋は「金」、冬は「水」、そして残った「土」が四季の変わり目に配置され、これが「土用」となったといわれています。また、昔の日本では日付を十二支で数えており、土用の期間中の「丑」に当たる日を「土用の丑の日」としました。12日ごとに巡ってくるため「一の丑」「ニの丑」と、二回訪れることもあります。
江戸時代に入ると、「土用の丑の日」を特に重要視するようになり、「う」のつく栄養価の高い食材、特に「うなぎ」を食べて夏の暑さを乗り切る風習が広まりました。また、夏バテ回復を目的に、薬草を入れた風呂「丑湯(うしゆ)」に浸かることや、お灸をすえる習慣も生まれました。ちょうど梅雨明けの時期と重なるため、衣類や書籍を風に当てて湿気を払う「土用の虫干し」や、梅干しを天日で干す「土用干し」にも適した季節とされています。
「夏土用」の行事食


「う」のつくもの
うなぎ、うし(牛)、うどん、梅干し、うりなど、「う」のつく食材には栄養価の高いものが多く、暑さで体力を消耗しやすい時期にぴったりであったことから、「丑(うし)の日」にちなみ、これらを食べる習慣が生まれました。うなぎを食べるようになったのは、江戸時代後期、蘭学者の平賀源内が売れ行きが不振だったうなぎ屋に相談を受け、「本日土用丑の日」の貼り紙を出して売るようアドバイスしたところ、大繁盛したことがきっかけといわれています。

土用しじみ
夏に旬を迎えるしじみは栄養価が高く、滋養強壮、疲労回復に役立つとされ、うなぎを食べる習慣が広まる以前から夏土用に食べられていました。

土用餅
やわらかくのばした餅を、こしあんやつぶあんで包んだ和菓子で、主に関西や北陸地方で夏土用に食べられています。小豆の赤色には邪気を払う力があるとされ、「魔滅(まめ)」の語呂合わせからも厄除けの意味が込められています。また、昔は貴重だった小豆や砂糖を摂り、夏の暑さに負けないよう栄養を補う目的もありました。
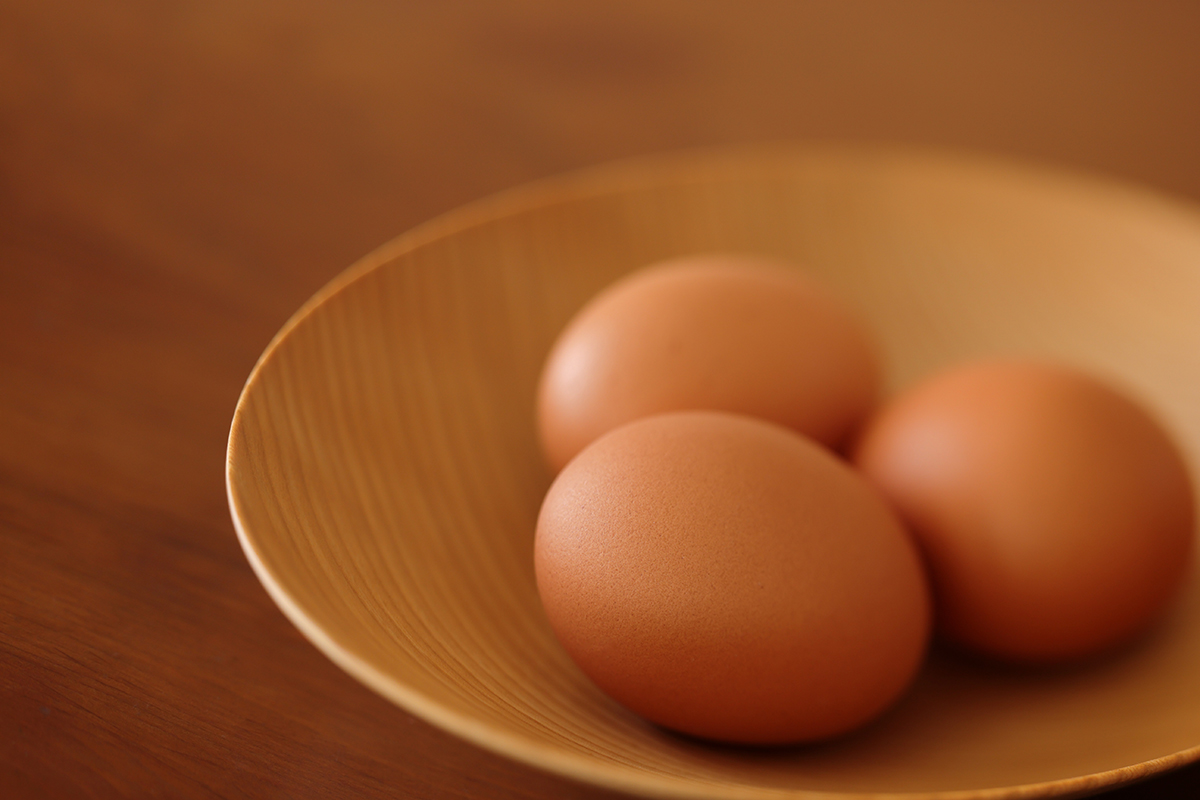
土用卵
土用の期間に産卵された卵のことで、特に精がつくといわれています。
